1月20日(月) 肘折温泉~米沢~飯坂温泉(福島県)
朝はまたゆっくり温泉につかり、9時50分のゆけむりラインで新庄駅に向かう。このバスは、温泉街のメイン通りを進むのだが、道の両脇の宿の人たちが外に出て、バスに向かって手を振ってくれていた。一期一会を大切にして、旅人との別れを惜しむようなおもてなしの心が暖かく心に響いた。
バスは坂道を登っていき、また眼下に肘折温泉街が見えた。今日は曇り空だったが、これが通常の東北の空なのだろう。その色彩のトーンが、またさらに肘折温泉街の風景を美しく見せていた。
10時45分、新庄駅着。11時13分の“つばさ140号”で米沢駅に向かう。この山形新幹線は、通常の列車の軌道を通るらしく、大雪が降ると動かないことも多いという風に聞いていたが、今日は雪も降らず順調に進む。米沢駅には12時37分着。

米沢駅の観光案内所で上杉神社に行く方法を聞くが、公共交通の便が相当に悪く、バスは1時間に1本程度なのだそうだ。駅から30分ほどかかるらしいが、歩いていくことにする。
今日は暖かく雪も降っていない。曇りだったが、次第に晴れてくる。しかし、道には大量の雪がある。車道は除雪してあるが、道の両脇には雪がうずたかく積もっている。駅の近辺なので、歩道も雪かきしてあるところが多く、なんとか歩くことができた。歩道もところどころ凍っていて、気を付けて歩かないと転んでしまいそうだ。歩くだけで相当に体幹が鍛えられそうだ。

目当ては“伝国の杜 上杉博物館”だったのだが、なんと今日は月曜日で休館日。残念。上杉神社にお参りすることにする。雪の中の神社。毘沙門天の毘の字の旗がある。ところどころに歴史由来等が書いてあり、歴史を知ることができる。また、米沢藩第9代藩主 上杉鷹山の像があったり、やはりこの名君主は米沢の人たちの誇りなのだと思う。上杉鷹山の“なせば成る なさねば成らぬ何事も なさぬは人の なさぬなりけり”と彫ってある。本当にそのとおりだとしみじみ思う。


上杉神社を後にして、また歩いて“酒造資料館 東光の酒蔵”に行く。ここは実際の酒蔵を改修して、伝統的な酒造りの方法を紹介しているところで、昔の酒造りを知ることができる。


巨大な酒樽なども展示されており、見ごたえがある。日本中の酒器の展示もあった。有料だが試飲ができるようになっている。

出口のところに上杉鷹山についての展示室あった。上杉鷹山は宮崎の高鍋藩主の次男として生まれ、母親は福岡県の秋月藩主の娘。祖母が上杉綱憲の娘で、秋月藩主黒田長貞の正室だったため、その時点で後継ぎがいなかった上杉家に婿養子として入ったのだそうだ。この名君主として名高い上杉鷹山が九州出身だったということをここで初めて知った。驚いた。
ひととおり米沢の観光を済ませ、また歩いて米沢駅に向かう。途中大きな寺や、都市の向こう側に雪を頂いた山があったりと、街の風景を楽しみながら駅に向かう。歩いてみるといろんな発見があり、その土地を身近に感じることができる。交通の便が悪いのが幸いして、逆にこの町を楽しむことができた。
米沢駅は15時40分発の山形新幹線つばさ146号に乗り、福島駅には16時14分に到着。福島駅に着いて驚いたことに、あの雪景色の米沢からわずか30分ほどしか移動していないのに、福島駅近辺には雪の形跡すらなかった。どこを見てもまったく雪がないのだ。気温も暖かく、この景色の急な変化は何なのだろうか。
福島駅から福島交通の電車に乗り今日の宿泊地 飯坂温泉に向かう。23分で飯坂温泉に到着。今日は有名な共同湯 鯖湖湯のすぐ近くにあるひろすけ旅館に泊まる。まわりに飲食店がたくさんあるようなイメージだったので、今日は食事をつけていない。でも、今日は月曜日。駅から宿までの間にある飲食店はほぼすべて閉まっていた。宿の人に食事ができるところを聞いて情報を集める。飲食マップが切れていたので、ご主人が急ぎ走って、観光案内所からマップを持ってきてくれた。
まずは腹ごしらえ。宿で教えてもらった、円盤餃子で有名な餃子屋 照井で食事をすることにする。店は客が多く、とてもにぎわっていた。円盤餃子は22個の上げ餃子を、皿に円く並べてあることから円盤餃子というネーミングになっている。22個の餃子と生ビールを注文。良い夕食となった。

それから、今日開いている駅近くの共同浴場 波来湯に行く。1200年の歴史ある温泉のようだが、建築の老朽化で2011年に建て替えられているので新しい。お湯は温湯と熱湯に分かれており、温湯が42度と書いてある。熱湯は45度らしい。
温湯も熱いが、気持ちよく入れるくらいの温度だ。となりの熱湯はかなり熱い。足がしびれるような熱さだ。しばらくは足がじんじんして、動くこともできない。我慢しながら入るが、一度入ってしまえば結構気持ち良い。飯坂温泉は熱いのが特徴のようだが、上がった後がいつまでもホカホカしてなかなか良い。ぬる目のお湯に長く入るのが好きなのだが、これは目が覚めるような熱さ。しかし入ってみるとこれはこれで最高だなと思う。
上がってから宿に戻る。宿の温泉は小さいが、41度設定のようでゆっくり入れた。
しばらく休憩して、また別の共同浴場に行く。川を渡り、仙気の湯に入る。ここも2つの湯舟があり、ひとつはなんとか入れる温度。42度らしいが、波来湯の42度よりも確実に熱い。もうひとつは手でお湯を触れただけでやけどしそうな温度。47度とある。地元の人が何人か来ていたが、誰もこの風呂につかろうとする人を見なかった。この温度で入ったらやけどしそうなので、熱湯に入るのはあきらめた。絶対に無理だと思う。

帰りも夜の街をぶらぶらと散歩しながら宿に向かう。飯坂温泉は日本武尊の東征の神話の時代から歴史がある温泉で、江戸時代には奥の細道の旅をしていた松尾芭蕉もここのお湯に浸かっている。しかし、泊めてもらったところが貧しい農家だったようで、土間にむしろをひいて寝たところ、ひどい雨漏りの中、蚤と蚊の攻撃を受け、また持病も再発する等、地獄のような経験だったということが、観光用看板に書いてあった。江戸時代も元禄の時代は、鄙びた田舎だったのだろう。しかし、その後の享保年間あたりから有名になり、町が開けていったようだ。

古い商家や蔵等も残っており、江戸時代から明治・大正、昭和頃にかけての、レトロな町並みを楽しむことができ、散歩するのが楽しい。川の両側にホテル・旅館が立ち並ぶ。しかし、つぶれて放置してあるようなホテルもちらほらと見える。
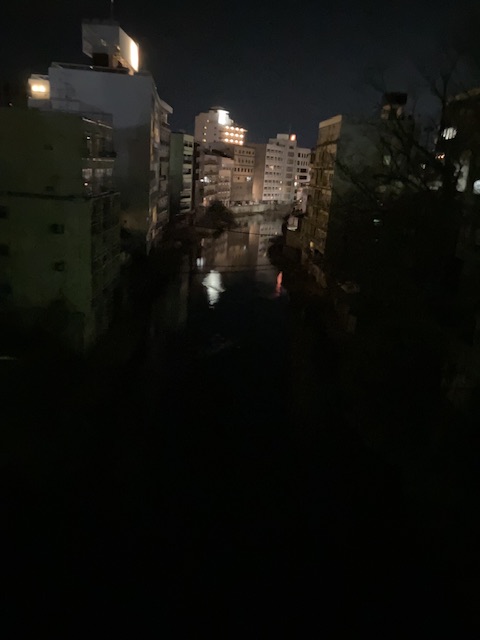



熱い温泉で温まったからだは、夜の街を散歩してもほとんど冷えることはなかった。

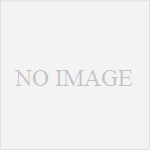
コメント